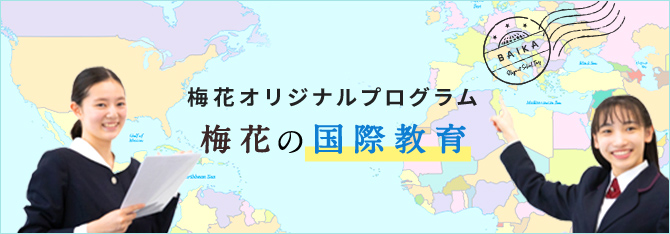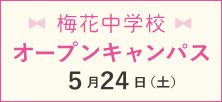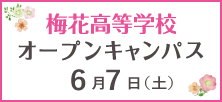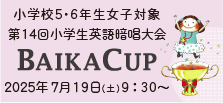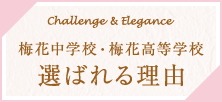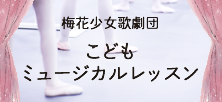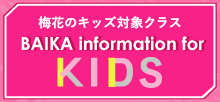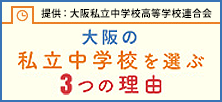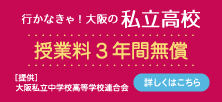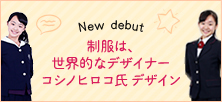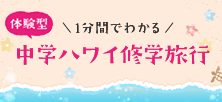総合進学専攻2年生の能楽体験の様子をお届けします。
2学期期末試験後の、リベラルアーツウィーク(特別プログラム実施によるスペシャルウィーク)のプログラムの1つになります。
江戸時代初期から250年以上続く能楽の家に生まれた能楽師である大西礼久先生をお招きし、お話しを伺いました。
能楽は室町時代から続く日本の古典芸能で、国の重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。大西先生ご自身も、重要無形文化財保持者でいらっしゃいます。




能楽は元々、男性芸能であり、男性が演じれないものに能面をつけるそうです。年齢・人物の気持ちに応じて様々な種類があり、役柄により使い分けられていることや、舞台に大きなセットを設置する事はあまり無く、能面の角度や所作で、気持ちや情景を表現するそうです。


実際に能面をつけさせて頂くと、視界はとても狭く一歩踏み出すのも恐る恐るといった様子。実際に能楽師が演じる時には、舞台の四隅に設けられた柱を目安に距離感を保つのだそうです。


装束の着付けも体験させて頂きました。着方によって表現する役柄も異なるらしく、滅多に見ることが出来ない着付け方や、華やかな衣装に生徒たちも興味津々です。


お囃子で使われる楽器についても、能楽は弦楽器を使わない世界的にも珍しい芸能であることや、4種の楽器でフルオーケストラとしての編成となること、楽器の特徴について詳しくお話ししてくださいました。


楽器体験では、生徒だけでなく先生も舞台に上がり、息を合わせて鼓を打ちます。


最後に、演目「土蜘蛛(つちぐも)」の一部を披露して頂きました。
優雅な中にも、力強さのある立ち振る舞いや、蜘蛛の糸を投げる仕掛けに目が釘付けになりました。
「楽譜はどうしているんですか?」「蜘蛛の糸の材質は何ですか?」「入門するにはどうしたらいいですか?」といった質問にも大西先生は丁寧に答えて下さいました。 3学期には大槻能楽堂での鑑賞会を予定しています。
3学期には大槻能楽堂での鑑賞会を予定しています。
能楽について学んだことを踏まえた新たな視点での鑑賞が楽しみですね。
2学期期末試験後の、リベラルアーツウィーク(特別プログラム実施によるスペシャルウィーク)のプログラムの1つになります。
江戸時代初期から250年以上続く能楽の家に生まれた能楽師である大西礼久先生をお招きし、お話しを伺いました。
能楽は室町時代から続く日本の古典芸能で、国の重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。大西先生ご自身も、重要無形文化財保持者でいらっしゃいます。




能楽は元々、男性芸能であり、男性が演じれないものに能面をつけるそうです。年齢・人物の気持ちに応じて様々な種類があり、役柄により使い分けられていることや、舞台に大きなセットを設置する事はあまり無く、能面の角度や所作で、気持ちや情景を表現するそうです。


実際に能面をつけさせて頂くと、視界はとても狭く一歩踏み出すのも恐る恐るといった様子。実際に能楽師が演じる時には、舞台の四隅に設けられた柱を目安に距離感を保つのだそうです。


装束の着付けも体験させて頂きました。着方によって表現する役柄も異なるらしく、滅多に見ることが出来ない着付け方や、華やかな衣装に生徒たちも興味津々です。


お囃子で使われる楽器についても、能楽は弦楽器を使わない世界的にも珍しい芸能であることや、4種の楽器でフルオーケストラとしての編成となること、楽器の特徴について詳しくお話ししてくださいました。


楽器体験では、生徒だけでなく先生も舞台に上がり、息を合わせて鼓を打ちます。


最後に、演目「土蜘蛛(つちぐも)」の一部を披露して頂きました。
優雅な中にも、力強さのある立ち振る舞いや、蜘蛛の糸を投げる仕掛けに目が釘付けになりました。
「楽譜はどうしているんですか?」「蜘蛛の糸の材質は何ですか?」「入門するにはどうしたらいいですか?」といった質問にも大西先生は丁寧に答えて下さいました。

能楽について学んだことを踏まえた新たな視点での鑑賞が楽しみですね。